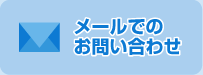現在の位置:トップ / 暮らしトップ / 暮らしのガイドライン / 日々のニーズから探す / 税金・国民保険・年金
国民健康保険料
国民健康保険料を納める人
保険料を納める人を納付義務者といいます。
国民健康保険では、加入者の一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納付義務者になります。
世帯主ご本人が、会社の医療保険などに加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、納付義務者となります。
国民健康保険料とは
年間の保険料は「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」の合計です。
・医療分保険料:加入者のみなさまが病気やけがをしたときの医療費等の給付にあてるもの
・後期高齢者支援金分保険料:75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支援するためのもの
・介護分保険料:加入者のうち、40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)に賦課されるもので、介護サービスに必要な費用等にあてるもの
国民健康保険料の計算方法
保険料は世帯単位で計算します。
「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」はそれぞれ「所得割」、「資産割」、
「均等割」、「平等割」の合計で決定します。
・所得割:加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算
・資産割:加入者の本年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)に応じて計算
・均等割:加入者一人あたりに決められた金額
・平等割:1世帯あたりに決められた金額
(注意)保険料を計算するために、所得がなかった人も申告が必要です。国民健康保険で受けられる主な給付
令和6年度保険料の計算式
・医療分保険料(加入全世帯)
・所得割=(令和5年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×4.85%
・所得割=令和6年度の固定資産税額×39.90%
・均等割=加入者数×25,000円
・平等割=1世帯あたり16,300円(特定世帯は8,150円、特定継続世帯12,225円)
・医療分保険料の限度額:1年あたり65万円
・後期高齢者支援金分分保険料(加入全世帯)
・所得割=(令和5年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×0.19%
・所得割=令和6年度の固定資産税額×1.55%
・均等割=加入者数×1,000円
・平等割=1世帯あたり600円(特定世帯は300円、特定継続世帯450円)
・後期高齢者支援金分保険料の限度額:1年あたり24万円
・介護分保険料(40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯)
・所得割=(令和5年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.70%
・所得割=令和6年度の固定資産税額×26.90%
・均等割=加入者数×13,200円
・平等割=1世帯あたり6,200円
・介護分保険料の限度額:1年あたり17万円
一世帯あたりの最高額
・40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯1年あたり106万円
・40歳から65歳未満の被保険者がいない世帯1年あたり89万円
・(注意1)特定世帯:同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、単身者となる世帯です
・(注意2)特定継続世帯:特定世帯が終了する年度の翌年度から3年間該当します
・(注意3)今年度中に75歳になる方:あらかじめ75歳になる月の前月までの月数分で医療分と支援金分保険料を計算しています。
・(注意4)今年度中に65歳になる方:あらかじめ65歳になる月(誕生日の前日が属する月)の前月までの月数分で介護分保険料を計算しています。
保険料の軽減
世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の所得の合計額が基準以下の場合、保険料のうち均等割と平等割が軽減されます。
軽減基準の所得額と軽減割合について
| 軽減割合 | 世帯主を含む国保加入者の前年中所得の合計 |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者の数ー1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(国保加入者数×29万5千円)+10万円×(給与所得者の数ー1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(国保加入者数×54万5千円)+10万円×(給与所得者の数ー1)以下 |
次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額が支給されます。
注意
・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)をいいます
・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数と所得を含みます
・所得未申告の方がいる世帯には、軽減が適用されません。必ず申告してください(ただし、収入が課税対象の公的年金のみの場合は申告の必要はありません)
・軽減判定をするときは、65歳以上の方で年金所得がある場合、その所得から15万円を控除します
・軽減判定をするときは、専従者控除は適用せず、専従者給与所得は含みません
・軽減判定をするときは、譲渡所得の特別控除は適用しません
未就学児の均等割保険料の軽減
令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯等による制限をかけず、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。そのため、被保険者のみなさまに申請していただく必要はありません。(注意)上記の保険料の均等割りと平等割の軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
非自発的失業(解雇や雇止めなど)による保険料の軽減制度
次の場合、届出により保険料が軽減されます。
対象者
・離職日現在に65歳未満であること
・雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
・ただし、「特別受給資格者」及び「高年齢受給資格者」の人は上記コードであっても対象外となります。(雇用受給者証の右上に「高」「特」とそれぞれ記載されています。)
軽減の内容
・保険料のうち所得割額について、対象者本人の給与所得を100分の30にしてから計算をします。
・保険料のうち均等割額と平等割額の軽減について、対象者本人の給与所得を100分の30にしてかっら判定をします。ただし、すでに国民健康保険に加入している世帯に、対象者が追加で加入される場合は、その年度の再判定は行いません。
軽減の期間
離職年月日の翌日からその翌年度末まで
届出に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・保険証
産前産後期間の保険料の軽減制度(令和6年1月1日施行)
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する人の産前産後期間の国民健康保険料を減額する制度が始まります。
出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
対象者
国民健康保険に加入している人で令和5年11月以降に出産する(した)人
(注意)妊娠85日以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)が対象です。
軽減の内容
出産(予定)日が属する月の前月から4ヵ月相当分の所得割額と均等割額を免除します。
多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月相当分を免除します。
保険料の減免
被用者保険の被扶養者であった人の保険料の減免
社会保険等の被保険者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合、申請により保険料が減額されます。
1.旧被扶養者にかかる所得割額:全額免除
2.旧被扶養者にかかる均等割額:半額に減額
3.旧被扶養者のみで構成される世帯:平等割額を半額に減額
注意
・国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である人のみ適用となります。
・均等割と平等割が7割軽減と5割軽減に該当する世帯は適用となりません。
・旧被扶養者の資格取得日の属する月移行2年を経過する月までの間適用します(所得割額については、当分の間免除します)。
被災、倒産、休業、廃業、疾病等による減免
保険料は主に加入者の前年中所得に基づいて決定しております。ところが、特別な事情により昨年と比較し現在の所得が著しく低くなり、保険料のお支払いが難しくなった場合、以下の条件を満たす世帯は申請により保険料が減免になる場合があります。
保険料減免の対象者
1.災害により生活が著しく困難とあった世帯
2.生計主体者またはこれに準ずる人の死亡により生活が著しく困難となった世帯
3.失業(退職の理由が自己都合退職、契約期間満了(雇用保険受給資格者証の離職コード24)、定年退職を除く)、休業、廃業または疾病等により所得が著しく減少した世帯。ただし、非自発的失業による保険料軽減に該当する人は原則として対象になりません。
保険料減免の要件
加入者の現在所得が前年所得の70%以下である場合、かつ世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の現在の世帯の総所得金額及び預貯金額が「知夫村国民健康保険料減免取扱要綱」の基準を超えない場合。

 08514-8-2211
08514-8-2211 08514-8-2093
08514-8-2093